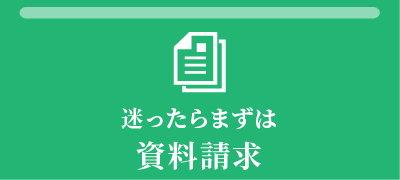賃貸物件を探す際、築年数と耐震性は大きな関心事ですよね。
特に地震が多い日本では、安心安全な住まいを選ぶことは非常に重要です。
古い建物は耐震性に不安を感じがちですが、築年数だけで判断するのは危険です。
今回は、築年数と耐震性の関係を分かりやすく解説し、賃貸物件選びの際に役立つ情報を提供します。
安心して暮らせる住まい選びのヒントになれば幸いです。
築年数と耐震性の関係を理解する
1: 築年数と耐震基準の変遷
日本の建築基準法における耐震基準は、過去の大地震を教訓に何度も改正されてきました。
1924年の関東大震災後の耐震規定を始まりとして、1958年、1981年、2000年と、重要な改正が行われています。
特に1981年の改正で「新耐震基準」が導入され、耐震性能が大きく向上しました。
このため、1981年以前の建物は「旧耐震基準」で建てられた可能性が高く、耐震性に不安が残るケースが多いと言えます。
2000年の改正では、特に木造住宅の耐震性能強化に焦点が当てられました。
2: 旧耐震基準と新耐震基準の違い
旧耐震基準は、震度5程度の地震に対して大きな損傷を受けないことを目標としていました。
しかし、震度6以上の強い地震に対しては、倒壊のリスクが否定できません。
一方、新耐震基準は、震度6~7程度の地震に対しても倒壊・崩壊しないことを目標としています。
これは、建物の構造や材料、接合部の強度など、様々な面での強化を意味します。
具体的には、必要な壁量や柱・梁の強度、接合部の金物などが厳しく規定されています。
旧耐震基準と新耐震基準では、地震に対する安全性のレベルに大きな差があることを理解しておくことが重要です。
3: 築年数別の耐震性に関する注意点
築年数と耐震性の関係は、必ずしも単純ではありません。
1981年6月1日以降に建築確認申請が提出された建物は新耐震基準に準拠している可能性が高いですが、それ以前の建物であっても、耐震補強工事などが行われているケースもあります。
築年数が古い建物は、耐震性に不安がある可能性が高いことは事実ですが、必ずしも危険なわけではありません。
築年数だけでなく、建物の構造、耐震補強の有無、建築確認日などを総合的に判断する必要があります。
特に、築40年以上経過した物件は、注意深く確認する必要があります。
4: 耐震性を確認する方法・建築確認申請日などの重要性
賃貸物件の耐震性を確認する最も確実な方法は、建築確認申請日を確認することです。
建築確認済証や検査済証などの書類に記載されています。
これらの書類を入手し、建築確認申請日が1981年6月1日以降であれば、新耐震基準に準拠している可能性が高いです。
ただし、書類がない場合は、不動産会社に問い合わせて確認する必要があります。
また、耐震診断書があれば、建物の耐震性能を客観的に評価できます。
耐震診断は専門業者に依頼する必要がありますが、より詳細な情報を取得することができます。

安心安全な賃貸物件選びのためのチェックポイント
1: 築年数以外の重要な要素 家賃・設備・立地など
築年数と耐震性に加えて、家賃、設備、立地なども賃貸物件選びにおいて重要な要素です。
家賃は予算に合わせて、設備は生活スタイルに合わせて、立地は通勤・通学の利便性や生活環境を考慮して選ぶ必要があります。
これらの要素を総合的に評価し、自分にとって最適な物件を選ぶことが重要です。
例えば、築年数が古くても、リフォーム済みの物件であれば、快適に暮らせる可能性があります。
逆に、築年数が新しくても、設備が古かったり、立地が悪かったりする物件もあります。
2: 物件選びにおける優先順位の決め方
賃貸物件選びでは、何を重視するかが重要です。
耐震性を最も重視するなら、新耐震基準で建てられた物件を選ぶべきです。
しかし、予算や立地などの条件も考慮する必要があります。
例えば、予算が限られている場合は、築年数が古くても家賃が安い物件を検討する必要があるかもしれません。
一方、通勤・通学の利便性を重視するなら、立地の良い物件を選ぶべきです。
自分の優先順位を明確にして、物件探しを進めることが重要です。
3: 専門家への相談や耐震診断の活用
賃貸物件選びに迷う場合は、不動産会社や専門家などに相談することをおすすめします。
不動産会社は、物件に関する様々な情報を提供してくれます。
専門家には、耐震診断やリフォーム・リノベーションなどの相談ができます。
耐震診断は、建物の耐震性能を専門的に評価するもので、より詳細な情報を取得することができます。
不安な場合は、専門家の意見を参考に、安心安全な物件を選びましょう。

まとめ
賃貸物件選びにおいて、築年数と耐震性は重要な要素ですが、それだけで判断するのではなく、家賃、設備、立地なども総合的に考慮することが重要です。
特に古い建物は、建築確認日を確認し、必要であれば耐震診断を依頼して、建物の耐震性を確認しましょう。
この記事が、皆さんの安心安全な住まい選びの参考になれば幸いです。
補足説明;耐震等級について
国が定める住宅性能表示制度により、建築物がどの程度の地震に耐えられるかを示す等級です。
建築基準法(2000年基準)の耐震基準相当で「耐震等級1」 その1.25倍ならば「耐震等級2」1.5倍ならば「耐震等級3」になります。
建築基準法レベルの等級1では、極めて稀に発生する大規模の地震に対して、倒壊・崩壊はしないことを求めるものの損傷する可能性はあるため、被害をより軽微とするためには、耐震等級3とすることが必須です。
震度6強~7の大地震時でも安心して住みつつ続けるには耐震等級3の認定収得が有効です。
耐震等級1 建築基準法(2000年基準) 極めて稀に発生する地震量に対して倒壊・崩壊しない程度
耐震等級2 等級1の1.25倍の耐震性能 病院や学校の耐震性に匹敵
耐震等級3 等級1の1.5倍の耐震性能 消防や警察など防災の拠点となる建物の耐震性に匹敵
旧耐震(1981年、昭和56年5/31以前)の建物は、圧倒的に 壁量が不足しており、耐震性能を確保するには、耐震診断を早急に行い、適切な耐震改修をすべきです。
耐震補強は耐力壁の増加とその配置計画、基礎補強となります。
1981年の改正後から2000年の改正前の新耐震住宅の問題点
2000年6月で、壁の配置バランスと金物の指定がはじめて明確化されたためそれ以前の建物は、接合部がくぎ打ち程度の状態であることもかなり多く、金物を使用している住宅も見られますが、この当時は国が定める明確な規定が ありませんので施工法も様々です。
ホールダウン金物の規定もこの当時はあり ませんので、柱が抜けてしまった被害も多くあります。
壁の配置もバランスを考慮されておりませんでした。
そのため、「新耐震住宅」ではあるものの2000年の現行基準を満たしていな場合が多い為、耐震性能においては既存不適格となります。
実際、熊本地震(震度7)では、前震・本震により 2000年基準以降の建物(耐震等級1)の住宅にも倒壊被害が発生しております。
住宅被害の大きかった益城町で、軽微な被害で済んでいる住宅を調べたところ、耐震等級3相当の建物が複数存在しておりました。
益城町の実状
倒壊 (破壊)
旧耐震基準 (1981年5/31以前) 214棟
新耐震基準 (1981年6月~2000年5月、
壁の配置バランスと金物の指定がはじめて明確化)76棟
新耐震基準(2000年6月~) 7棟
新耐震基準 (2000年6月~)耐震等級3 0棟
全壊(大破)
旧耐震基準 (1981年5/31以前) 133棟
新耐震基準 (1981年6月~2000年5月、
壁の配置バランスと金物の指定がはじめて明確化) 85棟
新耐震基準(2000年6月~) 12棟
新耐震基準 (2000年6月~)耐震等級3 0棟
耐震等級3のレベルならば、安全性は格段に向上します。弊社でも耐震等級3を推奨しております。
住まいの耐震性を自分でチエック!
Q1 2000年以前に建てた終えですか?
建築された年代により耐震性の基準が異なります。2000年以前い建てられた建物は、
現在より耐震基準が低く設定されています。
Q2 今までに大きな災害に遭ったことがありますか?
床上・床下浸水や災害、車の突入事故、大地震などに遭遇した建物は、外見では分かりずらい
ダメージが蓄積している可能性があります。
Q3 増改築をしたことがある?
建築確認などを省略して増改築してる場合や、増改築を2回以上繰り返している場合、また、その際に
壁や柱を撤去している場合は、注意が必要です。
3つの質問のうち1つでも当てはまれば耐震性に不安がありますので、ご相談して頂ければ幸いです。
1981年 昭和56年5/31以前の旧耐震の建物に関しても耐震補強は可能です。
地域によって異なりますが、国や地方公共団体からの補助金も利用できます。
追加の記事としてこちらもお読みください。
1981年 昭和56年5/31以前の旧耐震の建物をリフォームして売却する際の「3000万円の特別控除」の内容です。
これから、日本人の10人に一人が空家を所有することになりますが空家の問題には情報の整理が大切です。
例えば、実家の相続人が親などから相続した家を売る場合は、土地の長期譲渡の税率が20%課税されます。
譲渡所得=売却価格ー(取得費∔譲渡費用)
住宅用財産を譲渡した場合は3000万円の特別控除があります。
この特例は、あくまでも住居用で次の条件があります。
・相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。
・譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること。
例えば、譲渡所得3000万円の場合、600万万円の譲渡税がかかり、手元に2400万円しかの残りませんがこの特例を使えば600万円の税金はかかりません。
特例の条件で「譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること。」とありますが、旧耐震の建物、具体的には昭和56年(1981年)5/31以前の建物はこの耐震基準を満たしていませんので、耐震改修が必要です。
解体して売却する場合は、更地にすると固定資産税が3倍から6倍に跳ね上がりますので、売買契約成立まで待たれた方が得策です。